
|
b 突固め方法:A法−突固め層数:3、突固め回数:25、最大粒径:19mm c 直ナイフ:直ナイフは、鋼製で片刃の付いた長さ25cm以上のものとする。 (B) 試 料 試料は、鉄精鉱、粉コークス、重晶石、高炉スラグ、二酸化マンガン鉱石、蛍石等一部の物質を除き到着時の状態(湿潤状態)で約5kgを分取し測定を行なう。 (C) 試験方法 aモールドと底板の質量(m1)をはかる。 b試料をモールドに入れ、所定の突固め方法で締め固める。突固めは、堅固で平らな床の上で行ない、突固め後の各層の厚さがほぼ等しくなる様にする。 c突固め後の試料上面は、モールドの上端から僅かに上になる様にする。 d突固め後、カラーを取り外し、モールド上部の余分な試料は直ナイフで注意深く削り取り、平面に仕上げる。 eモールドと底板の上部に付いた試料をよく拭き取り、全体の質量(m2)をはかる。 (D) 計 算 突固めた試料の密度は次の式によって算出する。 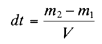
ここに、 dt:試料の湿潤密度(g/cm3) m1:モールドと底板の質量(g) m2:突固め後の質量(g) V:モールドの容量(1000cm3) (3) 運送許容水分値(TML)の測定(BC Code、Appendix D 参照) 選定された物質の運送許容水分値の測定は、IMOのBCコードに規定された試験方法により行なう。試験方法には、フローテーブル法、貫入法、ファガバーグ法の三法があり、通常、物質の性状、粒度等により最適な何れかの方法を選定し測定する。当初、フローテーブル法及び貫入法の二法により測定をする予定であったが、今回の試験対象は類似物質を主体とするので有効的な貫入法に限定し測定を行なうこととした。この類似物質は粒度の粗い物質及び粘土質の物質等が多く、フローテーブル法が適用できないケースがあるので貫入法のみを測定方法とした。測定条件に関してはIMO法を基準とし行なうことを前提とする。 (A) 試験装置及び試験条件 a 加 振 器:50Hz、2Grms b 筒形堆積容器:塩化ビニール樹脂製、容積 約1、700cm3(内径150mm×深さ200mm) c 貫入ビット :10kPa(微粉精鉱用)、真鍮製(177g) 5kPa(石炭その他用)、真鍮製( 88g) d タ ン パ ー:1994年度−バネ式タンパー等を適用 φ 30mm、40kPa( 2.8kgf) φ 60mm、62kPa(18.0kgf)
前ページ 目次へ 次ページ
|

|